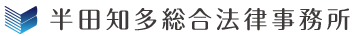【相続】遺言で法定相続人以外の者に財産を譲る「遺贈」について教えてください。

遺言で相続人ではない第三者に財産を譲る場合には「遺贈させる」文言の遺言を作成します。
遺言によって、相続人間の相続分及び遺産分割方法を指定することができます。では、相続人(以下、このコラムでは「相続人」を法律で定められている法定相続人という意味で使用します。)以外の場合に、遺言で財産を譲ることはできるのでしょうか。
生前に、第三者に財産を譲る(贈与する)ことが可能であるように、遺言によっても、もちろん財産を譲ることができます。これを「遺贈」といいます。
対抗要件の問題や農地法上の許可の問題から、相続人に対して「遺贈」文言の遺言を書くことはメリットがないとされ、実務上は行われていません。
そのため、平たく言えば、実務上、相続人に対して財産を譲り渡すには「相続させる」文言、相続人以外の者に対して財産を譲り渡すには「遺贈する」文言の遺言が使用されています。
相続人以外の者に財産を譲り渡すことがあるのかと不思議に思われる方もいらっしゃいますが、実は非常に多く、相続人に対して譲りたくない事情があり、生前お世話になった人に譲りたいケースがほとんどです。
「遺贈」には大きく分けて2種類あり、効果やその後に取る手続きもそれぞれ異なります。
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
「包括遺贈」とは、個別具体的な財産を指定せずに、財産を譲り渡す旨の文言の遺言を作成することをいいます。例えば、「私の全ての財産を〇〇××に遺贈する。」は包括遺贈です。
一方で、個別具体的な財産を指定して遺贈することを「特定遺贈」といいます。例えば、「私の〇〇銀行の預金を〇〇××に遺贈する。」は特定遺贈です。
遺贈の方法が包括遺贈か、特定遺贈かによって、実は大きく効果に違いが生じます。ここから細かく解説していきます。
「包括遺贈」では、受贈者は、債務(負債)も含めて、相続人と同様の扱いがされます。
民法990条で、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」とありますので、包括遺贈を受けた者、つまり包括受贈者は、相続人として取り扱われることとなります。
例えば、相続人が法定相続割合に応じて相続債権者に対して債務を負うように、包括受贈者は相続における債務に関しても負うことになります。
そのため、相続の承認・放棄に関する規定も準用され、包括受贈者は、法定相続人と同様に、「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3か月以内(期間伸長があれば6か月以内)に放棄をするかを決めなければなりません。
また、包括遺贈が「私の財産の3分の1を〇〇××に遺贈する。」という財産の一部に対してされた場合(「一部包括遺贈」といいます。)には、包括受贈者は、「相続人と同一の権利義務を有する」のですから、遺産分割協議にも参加することとになります。
なお、遺言によってされる包括遺贈のほとんどは、「自分の財産を全部遺贈する」文言の遺贈(「全部包括遺贈」といいます。)ですが、その場合には他の相続人から遺留分減殺請求に直面することも多いです。
「特定遺贈」の場合には、相続人と同一の権利義務を有せず、債務も承継しません。
一方、「特定遺贈」の場合には、指定された個別具体的な財産のみが受贈者に与えられることになります。
包括遺贈のように相続人と同様の権利義務を負うわけではないため、相続債務を承継しません。遺贈の対象財産が遺産から外れるのみであり、受贈者が遺産分割協議に参加することはありません。
では、相続債務があるにもかかわらず不動産の特定遺贈が行われた場合、相続債権者が特定遺贈の対象の物件から回収ができるのでしょうか。この場合には、相続債権者と特定受贈者は対抗関係に立つとされており、相続債権者の差押え登記と特定受贈者の遺贈の登記の先後関係によるとされています。
愛知県弁護士会所属
愛知県半田市で相続・離婚・交通事故・債務整理・中小企業法務を主な業務内容として、知多半島地域を中心に弁護士活動を行っております。
依頼者のために「真摯に・誠実に・最善を尽くす」を理念として半田知多総合法律事務所の運営にあたっています。
相談予約フォームは24時間受付中

半田知多総合法律事務所への相談予約は、お電話(0569-47-9630)だけでなく予約専用フォームからも可能です。
予約専用フォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットから受け付けており、24時間いつでも送信可能ですので、便利です。
お問い合わせいただいた場合には、営業時間内にご希望の返信方法に合わせて、返信させていただきます。